家庭菜園にはいろんな野菜の栽培方法がありますが簡単そうで意外にも難しい ’ほぼほったらかし栽培’
簡単そうで意外にも難しい・・・理由が、残念ながらありましてそんなほぼほったらかし栽培の裏事情!のリアルです
当サイトは商品のプロモーションを含みますお子様にも安心!”添加物不使用”のつくりおきおかずはじめまして、サイトへご訪問下さりありがとうございます。配信者は、愛知県の田舎で幼い頃から身近だった畑を2019年暮れから再開し、家庭菜園をほぼほったらかし栽培で野菜を育てている主婦です。当サイトは2023年8月から開設し、AIではなくわたし個人の主観や経験した内容を配信者本人が書いています(栽培エリア/中間地)
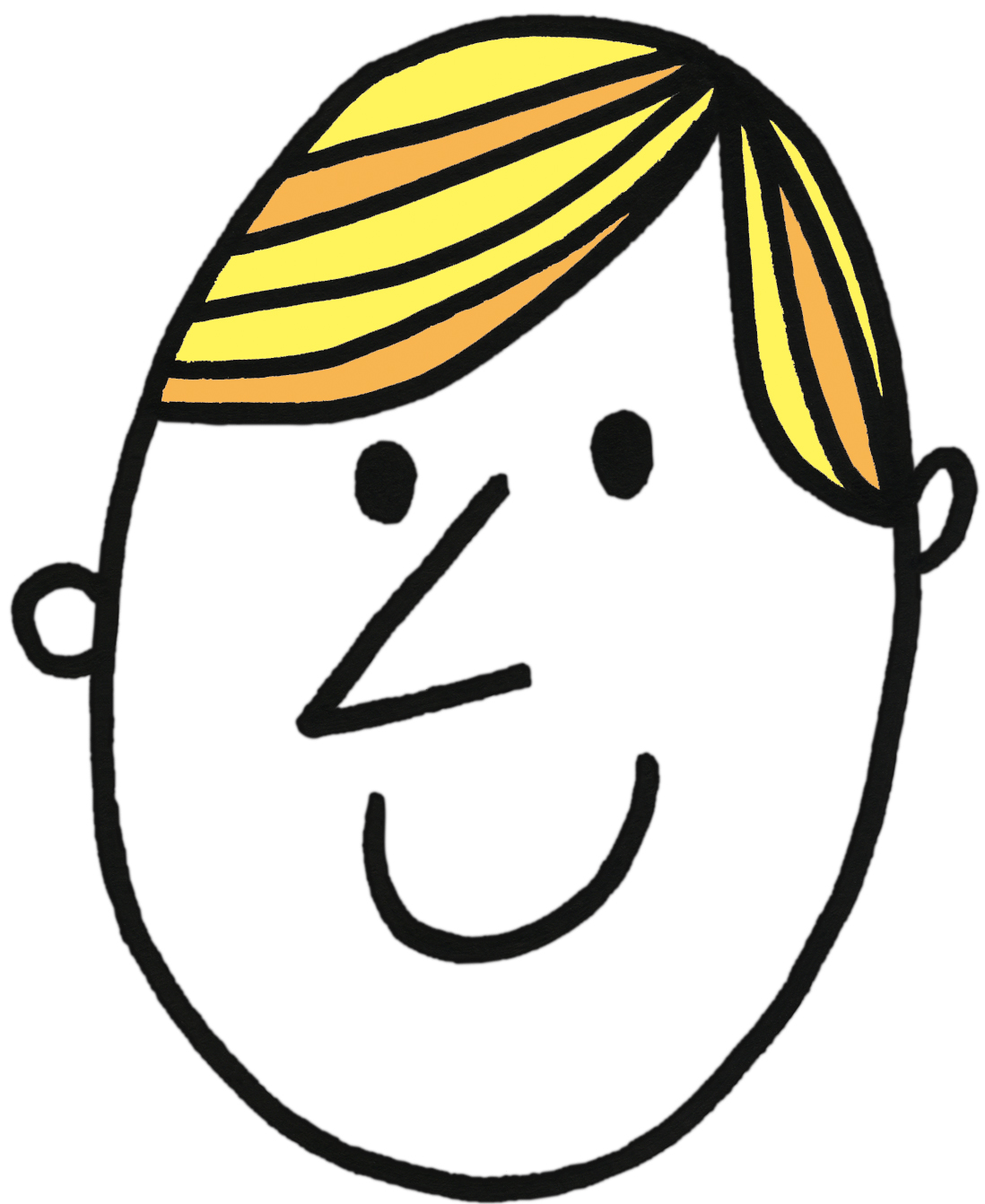
ほぼほったらかし栽培に興味があり
挑戦してみましたが
ぜんぜんうまくいきませんが
何が悪いのでしょうか?
こんなご質問につきまして…ほぼほったらかし栽培で、もし野菜が収穫できたらこんな節約方法はない!多くの方に周知されているかとおもいますが
◎これから家庭菜園を始めようとおもっている方
◎なかなかうまくいかない方
へ誇張したり、期待させたりすることなくほぼほったらかし栽培の裏事情として家庭菜園を続けている主婦がまとめています
✅ほぼほったらかし栽培で失敗続きの野菜たち
ここでは特に夏野菜の栽培の失敗談をお届けします
収穫前に枯れてしまったり、花が咲いても実がならなかったりと収穫できなかった、もしくは収穫しても1個か2個くらいしか収穫できない、こんな現実もあります

ナス科です。トマト、ナス、甘長とうがらし、ピーマン👆 ほぼ買っている野菜たちです。個人的にナス科の野菜の栽培難易度は非常に高いです

葉野菜です。茎レタス、キャベツ、からし菜、サニーレタス、サンチュ👆収穫できたり、買ったりしている野菜たちです
(白菜に嫌われている?とおもうほど白菜の栽培経験が今だありません。泣けちゃう)

瓜科です。カボチャ、ゴーヤ、瓜、冬瓜👆収穫できたり、できなかったり。年によって変わるので収穫結果はまちまちです
というかんじで不作、失敗の原因の一つには、猛暑、そして雨が降らない!ことが考えられます
家庭菜園をはじめたばかりの2020年~2021年は、少ないといっても殺人的な暑さではなかったし、適度に雨が降っていました。記憶あるのは2023年以降です。年々ひどくなっていく夏の気候。たった数年ですが、気候変動の異常さを体感しました
そんなこともあるんですよね。家庭菜園って、予想外のこともあるものです
そうなるとぶっちゃけ家庭菜園を0円でやることはほぼ難しいです
便利でよさげな菜園グッズは多種多様に売られているし、中には栽培効率がめちゃくちゃ上がりそうな便利アイテムもある。怪我をしないように自分の身を守るアイテムも必要になることでしょう
タネや肥料などのケミカル剤は年々高くなる一方だし、少しでも食費を抑えたい!との家庭菜園熱を冷めさせるばかり。これでは寂しすぎる裏事情でした
農家さんの野菜を買っています👇

✅タネは固定種を買って、苗を育てた
配信者の家庭菜園で買っているタネたちです👇

この手の種は栽培に強い、との所説ありますがトップ画像のように見事に枯れてしまいました
F1種のタネや苗だったらボコボコ実が成るのに・・・というアドバイスは正直あるので、家庭菜園初心者さんには迷いますよね。ということで
ほぼほったらかし栽培の裏事情!
タネや苗は、固定種(在来種)なのに失敗してしまいました
✅土の状態は良くなっていた

家庭菜園を始めて4年くらいした頃、畑の土にはこんなかんじの白い綿、糸のような菌がたくさん広がっていました
土の中では微生物がたくさん生きているので、こうした糸状菌が豊かであると土は活性している証でもある、と習いました。キノコもたくさん生えてきましたよ~

ということで ほぼほったらかし栽培の裏事情! 土の状態について、糸状菌や天然キノコが生える肥えてきた土でも失敗しました。まだまだ土の勉強が足りない配信者でした
✅浸水被害対策;畝高もあったし、床堆肥もした

配信者が畑をやっている地域では、梅雨の時期になると雨で浸水被害が起こります。画像はトマトではなくてネギの畝ですが、こんなかんじに畝高を30~40センチくらい整えて浸水被害の影響を最小限に抑える対策をして野菜を栽培しています
また、畝の底には畑で刈った枯草を混ぜておきました。微生物の活性を期待するためです。ということでほぼほったらかし栽培の裏事情! 畝高や床堆肥をしたのに失敗しました
✅水やり

とにかく2024年は雨がまったく降らない日が続きまして土が割れてしまったり葉がしおれていたりと
散々でした。ということで
ほぼほったらかし栽培の裏事情!
水やりをこまめにしたのに失敗してしまいました。これを課題にして土の中深く水分のある層まで根を張り日照りが続いても枯れにくいイネ科のハト麦をそばに植えて対策したいとおもいます
✅肥料や栄養剤をあげれば良かったのでは?
とのアドバイスは配信者の周りからもよく言われます。今は基本、自然農法に習ってやっているので
人工的なケミカル剤は散布しない方法をとっています
ということで ほぼほったらかし栽培の裏事情! 肥料や栄養剤をあげないけれど失敗してしまいました
まとめ
以上
ほぼほったらかし栽培の裏事情!
●固定種(在来種)なのに失敗
●糸状菌や天然キノコが生える肥えてきた土でも失敗
●畝高や床堆肥をしたのに失敗
●水やりをこまめにしたのに失敗
●肥料や栄養剤をあげないで失敗
でした。自然農法という単語がこのページで出てきましたがそもそも自然に寄り添ったやり方で、野菜の栽培に実際成功している方によると…
その土、その畑がそもそも元気なのか、弱っているかは、かつてどのような状態環境にあったかによって異なるので始めて見ないと正直分からない!
なので5年以上うまくいかない年が続くこともあり得るのが現実です。
確かこのようなことを聞いたことがあるので配信者がやっている畑は元慣行農業を5年以上していたため土が弱っていた、のかもしれません
ということで参考になったら嬉しいです!
野菜の栽培は風土、種子の種類、畑の土壌環境、また調理では衛生管理や調理場の環境の違いから、記事内と同じ結果にならない場合があります。予めご了承下さい【国産素材】無添加調理”FIT FOOD HOME”。人気ブログランキング








コメント